


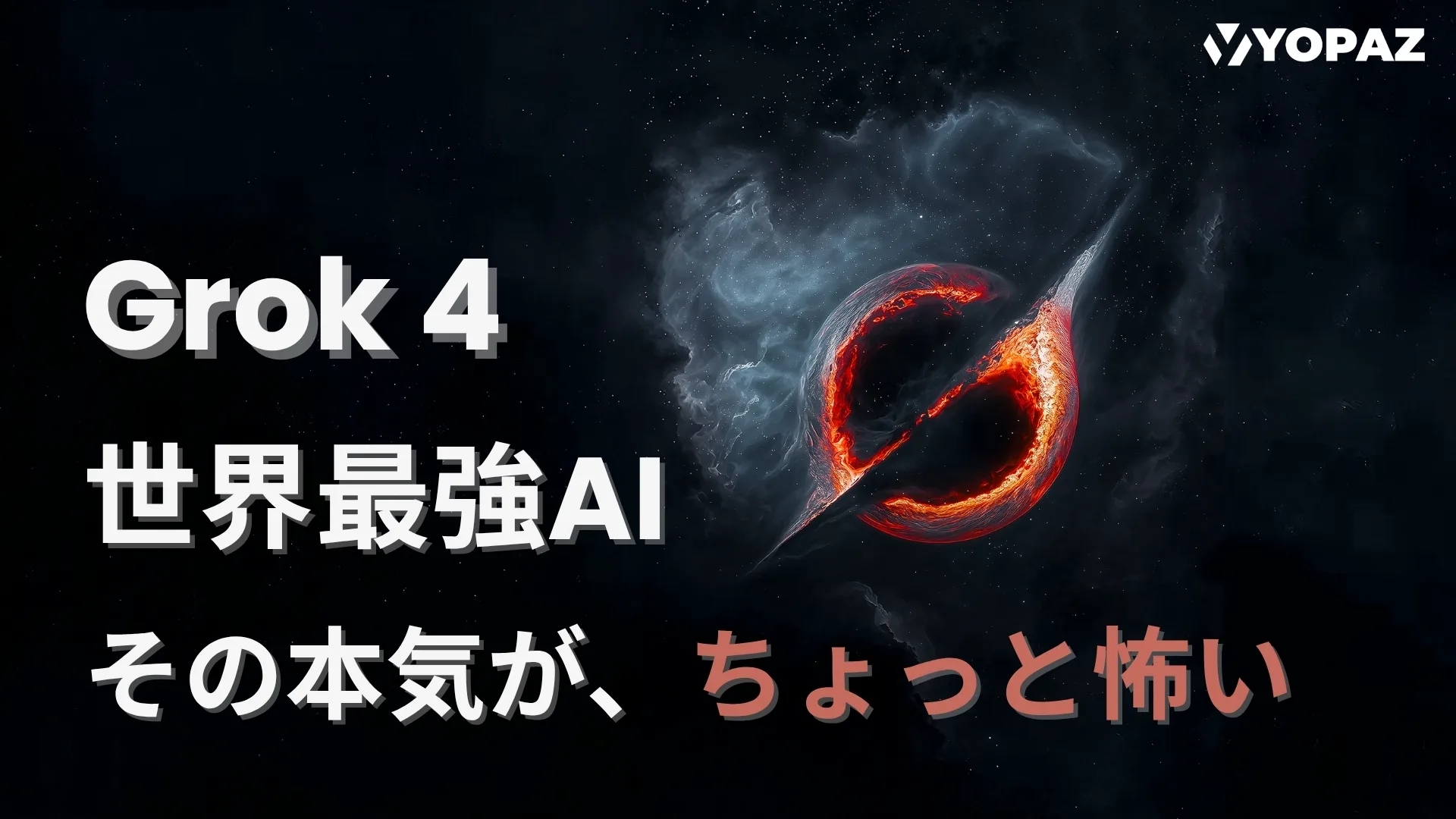
急速に発展するテクノロジーの時代において、農業DXは、農業分野において生産プロセスを最適化し、効率を向上させ、持続可能な発展を目指すための必然的なトレンドとなっています。
本記事では、農業DXの概念、利点やスマート農業との違いに加えて、農業にデジタル技術を導入する流れについて詳しく解説します。
農業DXを知りたい方はぜひ最後までご参考にしてください。
「農業DX」とは、デジタル技術を農業のあらゆる側面に適用するプロセスを指します。
具体的には以下のような技術が含まれます。
農業DXは、最新の技術を活用することで、従来の農業と比べて多くの利点をもたらします。
関連記事:
【2025年最新】ビッグデータの動向:日常生活に広がるデータ革命
AIとIoTの違い・関係性・活用事例を解説|2025年の最新動向も紹介
農業DXとスマート農業はどちらも農業分野における技術活用に関する概念ですが、その範囲や目的には違いがあります。ここから、その違いを詳しく説明します。
|
比較項目 |
農業DX |
スマート農業 |
|
運用範囲 |
生産・加工・流通・消費まで、農業全体を対象とする |
主に農場や圃場での生産工程に焦点を当てる |
|
重要技術 |
・ビッグデータ分析 ・ブロックチェーンを活用したトレーサビリティ管理 ・クラウドコンピューティング |
・IoTセンサーによる土壌や作物の監視 ・ドローンやロボットによる自動化 ・AIによる作物データ分析 ・自動潅水システム |
|
主な目的 |
・農業のデジタルエコシステムを構築 ・サプライチェーン全体の最適化 ・農業の持続可能性と価値向上 |
・労働負担の軽減 ・生産性、品質の向上 ・資源の無駄を削減 |
|
実例 |
・ブロックチェーンで農産物のトレーサビリティを管理 ・市場データを分析し、需給バランスを最適化 ・クラウド型農場管理システムの導入 |
・ドローンによる作物の監視 ・農薬散布 ・収穫ロボットの活用 ・IoTセンサーによる土壌の水分量管理 |
|
メリット |
・農業、企業、消費者間のデータ連携を強化 ・データ管理と資源の最適化 ・食の安全性向上とトレーサビリティ強化 |
・労働コストの削減と作業効率化 ・精密農業による収穫量と品質の向上 ・資源の適正活用による環境負荷の軽減 |
まとめ
農業DXは 農業全体のデジタル化 を推進する概念であり、生産だけでなくサプライチェーンや消費者向けの流通管理も含まれます。
スマート農業は 生産現場の自動化・最適化 に特化し、IoTやAIを活用して作業の効率を向上させます。
簡単に言えば、スマート農業は農業DXの一部 であり、農業DXはより広い視点から農業全体のデジタル変革を目指す概念です。
日本の農業は、高齢化や労働力不足といった深刻な課題に直面しています。これらの問題を解決し、農業を成長産業へと転換するために、デジタル技術を活用した農業DXが注目されています。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によれば、農業・林業におけるDXの取り組み状況は約45.4%と全平均を20%以上を上回ります。
出典: 独立行政法人情報処理推進機構 「IPA DX白書2023」第2部 国内産業におけるDXの取組状況の俯瞰 P9(図表2-6))
これから、取り組み内容についてご紹介します。
農林水産省は、2024年2月に「農業DX構想2.0」を発表し、デジタル技術を活用した農業の変革を推進しています。 この構想では、消費者ニーズをデータで捉え、効率的な生産・流通を実現する「FaaS(Farming as a Service)」への転換を目指しています。
具体的な取り組みとして、AIやIoTを活用したスマート農業技術の導入が進められています。自動運転トラクター、ドローンによる農薬散布、土壌センサーによる水分管理など、最新技術を積極的に活用します。
例えば、従来の農薬散布は手作業が多く、労働負担が大きかったが、ドローンを活用することで作業時間を大幅に短縮します。
しかし、手作業では1時間かかる散布作業を、ドローンならわずか10分で完了できます。また、AI搭載ドローンは病害虫が発生している場所を自動検知し、ピンポイントで農薬を散布することも可能になります。
関連記事:【2025年最新】今後AIが導く!各業界でのDX推進成功のカギ
農業DXが日本で強く推進されているのは、主に 労働力不足や生産性の向上、環境問題への対応、グローバル競争への適応 といった社会的・経済的な要因が関係しています。
それでは、農業DXを推進している背景を一緒に調べてみましょう。
(1) 急速に進む農業人口の減少
日本の農業就業人口は年々減少しており、2023年時点で 128万人(2020年は136万人)となっています。
1990年には約500万人の農業従事者がいたことを考えると、この30年で 約75% 減少していることになります。
(2) 農業従事者の高齢化
2024年時点で 農業従事者の平均年齢は67.9歳 に達しており、今後さらに高齢化が進む見込みです。
若い世代の農業離れが進んでおり、 新規就農者の数が十分ではない ため、後継者不足が深刻な問題となっています。
➡ 農業DXによる自動化・効率化が、少ない労働力で持続可能な農業を実現する鍵となる。
(1) 日本の農業の生産性は低い
日本の農業生産性(農業1人あたりの付加価値)は アメリカの約1/3、オランダの約1/2 と低い水準にあります。
一般的な農家では、 労働集約型の作業が多く、収益性が低い ことが課題となっています。
(2) 農業DXによる生産性向上の期待
農業DXによって、 データを活用した生産管理や、AI・ロボットによる作業の自動化 を進めることで、以下のような効果が期待されています。
➡ 農業DXは、労働力不足を補いながら生産性を向上させ、農家の収益を安定させる手段となります。
(1) 気候変動の影響による農作物被害
日本では、近年 猛暑や集中豪雨、台風の大型化 など、異常気象が頻発しています。そして、気候変動が農業に大きな影響を与えています。
(2) 持続可能な農業の実現
農業DXの技術を活用することで、環境負荷を減らしながら生産性を向上させることが可能になります。
例えば、 精密農業(スマート農業) によって、必要最小限の農薬や肥料で生産することで、環境にやさしい農業を実現できます。
スマート灌漑システム を活用すれば、水の使用量を大幅に削減し、持続可能な農業を推進できます。
➡ 農業DXは、気候変動の影響を軽減し、環境負荷を抑えながら安定した農業生産を可能にします。
(1) 海外市場の拡大と競争力向上
日本の農産物は高品質で人気があるものの、 価格が高いため国際競争力が低い という課題があります。
農業DXによるコスト削減・効率化 を進めることで、価格競争力を強化し、海外市場でのシェアを拡大することが期待されています。
(2) ブロックチェーンによるトレーサビリティの確保
農産物の生産・流通データを ブロックチェーン技術 で管理することで、食品の安全性を証明し、輸出促進につなげる動きもあります。
例えば、日本の高級果物や和牛などは 生産履歴を可視化することで、より高い付加価値をつけて販売 できるようになります。
➡ 農業DXによって、国際競争力を強化し、日本の農産物の輸出を拡大することが可能になります。
これらの要因が相まって、日本の農業はデジタル技術を活用した大きな変革の時期を迎えています。農業DXが本格的に進むことで、持続可能で競争力のある次世代農業が実現できるでしょう。
農業DXの導入には、計画的なステップが必要です。具体的に、以下のように4つのステップがあります。
|
まずは、自分たちの農業経営のどこに課題があるのかを整理します。それから、 DX導入の目的を明確にします。例えば、労働時間を30%削減します。
(1) 農業DXに関する情報を収集
(2) 導入する技術を選定
農業DXの技術には、以下のような種類があります。
➡ 課題に合った技術を選ぶことが重要です!
(1) いきなり全体導入せず、試験運用を行う
例えば、
画像認識に興味がある方はぜひこちらの【2025年最新】画像認識の動向:機械が「見る」、そして「理解する」世界へをご覧ください。
(2) 期待する成果が得られるか検証
試験導入の結果を踏まえて、最も効果の高い技術を本格導入します。
それから、データ活用を習慣化できるように現場のスタッフのための操作方法の研修を行います。
農業DXを成功させるには、「導入して終わり」ではなく、継続的な改善と活用が重要です。最適な技術を選び、実際の農業経営に適用しながら、持続可能なスマート農業を実現していきましょう!
農業DXは、デジタル技術を活用して農業の生産性や効率性を向上させる取り組みですが、その推進にはいくつかの課題が存在します。
課題:
日本の農業は小規模経営が多く、大規模投資が難しい現状があります。
解決策:
課題: 高齢の農業従事者を中心に、デジタル技術の習熟度が低い場合があります。
解決策:
課題: 異なるシステム間でのデータ連携が難しく、効率的な情報共有が阻害されています。
解決策:
課題: 最新のデジタル技術の導入には高額な初期投資が必要であり、特に小規模農家にとっては大きな負担となります。
解決策:
2025年における農業DXの動向は、技術の進歩と市場の拡大が顕著です。では、いくつかの主な動向を見てみましょう。
スマート農業関連の市場は、2025年までに大幅な成長が予測されています。特に、農業用ドローンの市場規模は2025年に1,073億円、農業ロボットは665億円、収穫ロボットは200億円、植物工場関連は541億円に達すると見込まれています。
出典:『2030年のフード&アグリテック』(NAPA編)の市場規模予測値
農林水産省の目標である「2025年までに農業の担い手のほぼ全てがデータを活用した農業を実践」に向けて、データ活用の取り組みが進んでいます。
2021年時点で、データを活用した農業を行っている経営体の割合は48.6%に達しており、今後さらに普及が期待されています。
農業DX推進のため、政府、企業、学術機関、金融機関が連携し、課題解決に向けた具体的な取り組みが活発化しています。
例えば、「食の未来会議2025」では、スタートアップ企業や関係者が集まり、農林水産業の革新に向けた議論が行われています。
AI(人工知能)の進化により、農業分野でも作物の生育予測や病害虫の早期発見など、精密農業への応用が進んでいます。これにより、生産性の向上やリソースの最適化が期待されています。
2025年の農業DXは技術革新と多方面の連携により、持続可能で効率的な農業の実現に向けて大きく前進すると考えられます。
農業DXはもはや遠い未来の話ではなく、現代農業における重要な要素となっています。デジタル技術の活用により、生産性向上、環境負荷の削減、製品品質の向上が期待できます。
今こそ、企業や農家がこの変革の波に乗り、農業の新たなステージへと進むべき時です。